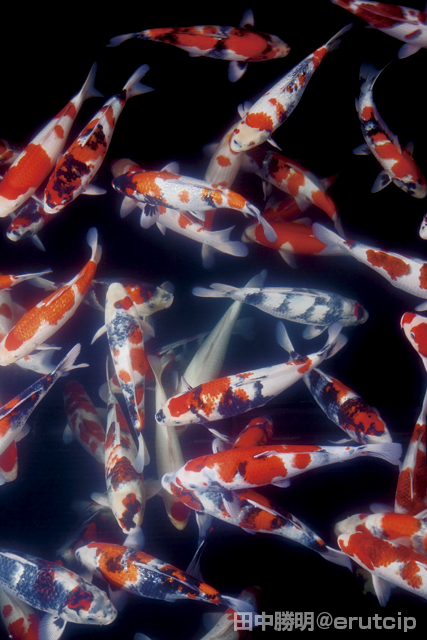雪国に息づく伝統の技術は、創造意欲と先見性のたまもの - 十日町

豪雪地帯の農閑期が生んだ芸術品 模様がカスレて見えるから「絣(かすり)」と呼ぶのだといいます。あらかじめ模様を染め込んだ絹糸を織機で交差させると出来る絣模様は、確かに交差の微細なズレによってカスレているように見えます。 「絹糸に糸をくくり付けておいて、これを染料につけると、くくった部分だけが白く残る。この白い部分が織り上げた時に模様となります」と話すのは、「十日町絣」を織り続ける伝統工芸士の渡邉孝一さん。ご両親も伝統工芸士として一つ屋根の下で絣織りに明け暮れます。 十日町絣は、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の両方を染め分けて、織機の上で模様を再現します。基本の絵柄は20種類程度。模様のパターンは方眼紙を使って考案されます。絣模様の大小や組み合わせ、色などを変えて、バリエーションを増やしています。 「伝統的な模様とはいえ、少なからず流行はありますよ。今ならこんな感じ」と出してくれた反物が前ページの3点。1反が13m。反物をここまで織り上げて1着の着物を作るには、最低でも3カ月はかかります。冬のほとんどが雪のため外から閉ざされてしまうこの地域では、その昔、機織りは長い農閑期の生業でした。そこらじゅうの農家から織機の音が響いていました。現在、十日町絣を織っているのは、渡邉さん一家を含めわずか5、6軒だけとなりました。 麻から絹への大転換 十日町の織物史をひも解いてみると、他の地域にはない変遷をたどっています。 十日町で絣織りなどの絹織物の生産が始まったのは、今から200年前の江戸時代後期から。一帯はもともと麻織物を作る技術も盛んで、その集大成とも言われる高級夏織物の「越後縮」を産出しています。越後縮は幕府の御用縮にも指定されており、江戸末期まで武士や上流階級を中心に幅広く供給されました。ところが明治になると木綿や絹織物が普及し、麻織物は衰退。この機に十日町は、いち早く絹織物の産地へと転換を遂げます。こうして麻織物の技術と伝統を生かした「十日町絣」が誕生しました。 やがて、絹織物の産地として歩み出した十日町に最初の大ヒット作「明石ちぢみ」が登場します。播州明石で生まれて京都西陣を経て、明治20年頃に十日町で完成を見た明石ちぢみは、シャリッとした清涼感のある夏の着物です。1929(昭和4)年には「越後名物かずかずあれど、明石ちぢみに雪の肌……」と唄われるほどの人気を博しま...